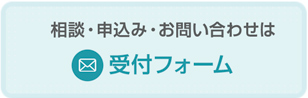過去を遡れば、日本において現在のような個人向けの住宅ローンが一般化したのは1950年の住宅金融公庫の設立によるとされます。公庫による公的住宅資金融資制度は、小泉内閣当時の2007年に住宅金融公庫に代わって住宅金融支援機構が設立されるまで続きましたが、その間における返済期間は基本最長25年でした。それが2003年の「フラット35」の登場で一気に35年まで延長されたわけですが、その背景には、供給側の事情としてのローン債権証券化手法の普及による超長期固定ローンの組成の実現があり、需要側の事情として、経済の長期停滞下での家計収入の伸び悩みの中で住宅需要を刺激する必要性が生じたことが挙げられます。しかしその間、2003年時点における公庫融資の延滞率(6か月以上)が融資残高の1.1%だったのに対し、直近2018年の支援機構における延滞率(3か月以上)は1.69%、貸出条件緩和分を含めると3.94%であり(機構の延滞率については、旧公庫分の延滞率が3%を超え、機構分は1%に満たず、それは公庫時代のローンの融資基準が甘かったからだとする指摘がありますが、現に何らかの事情で返済に支障をきたしている世帯が3.94%あるという事実は変わりません)、返済期間が25年と今より短く、また金利も今よりはるかに高いという、返済の条件が今より厳しかったはずの当時の環境を考慮すれば、やはり近年、ローンの返済リスクは高まっているとみなさざるを得ないでしょう。
またこういう見方もあります。日本においては、2012年時点ですが、それまでに全住宅資産に投じられた資金合計875.8兆円に対して、ストックとして残った住宅資産は339.6兆円に過ぎません。なんと536兆円もの住宅投資資金が喪失しているのです。そしてその間の1世帯当たりの住宅・宅地の減価は約2000万円に及ぶとの国交省の推計です。つまり、せっかく多額のローンを組んでマイホームを持っても、最終的に資産として残る価値は半分にも満たないということなのです。なぜこのようなことになるのでしょうか。その大きな原因の一つは、日本の木造家屋の資産的価値が22~23年でほぼゼロになることにあります。また人口減・世帯減・家余りの今後の日本においては、土地の資産価値もおそらく確実に下がるでしょう。これらのことから判断しても、やはり35年返済は制度的にあり得ません。返済期間25年が妥当な制度設計上の返済期間の上限なのではないでしょうか。35年ローンでは、手に入れた住宅資産の価値がゼロになって以降も、なお10年以上に渡って利息分も含む返済だけが残ることになります。また返済期間の長いローンを市場に投入すればするほど、より返済リスクの高い債務者を増やしてしまうことにもなります。
結論を申しあげれば、返済期間を長期化して1回ごとの返済額を下げても、それは見せかけの借り安さであり、リスクの先送りに過ぎません。「働き方改革」が叫ばれるなか、70歳定年制は、70歳まで国は面倒を見ないということの裏返しでもあります。20年30年先の収入など、たとえ上場企業の正社員とて読み切れない、加速度的に社会の変化のスピードが速まるこれからの時代を見据えたとき、 (勿論、今回のコロナ禍のような不測の事態に直面して家計が切迫したときには、返済期間の繰り延べなど、臨機応変な対応が必要ですが)、無理のない程度に繰り上げ返済に励むことは、引き続き基本戦略ではありますが、ローン返済計画としては、長くても、やはり基本25年返済をベースに設計すべきと考えます。